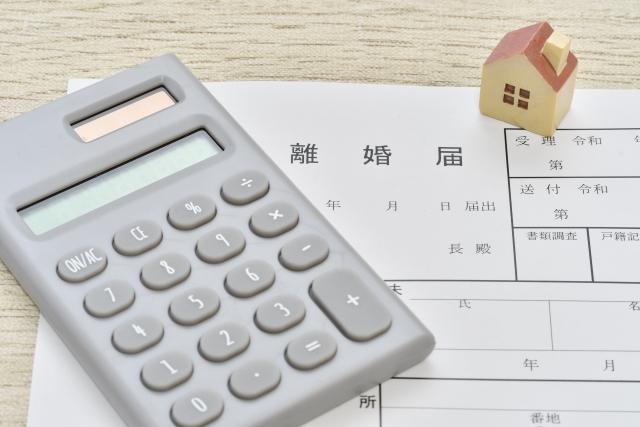相続が発生したとき、すべての相続人を把握しなければ手続きを進められません。
相続人の調査は自ら行うこともできますが、専門家へ依頼することも可能です。
この記事では、相続人の調査を弁護士へ依頼するメリットについて解説します。
相続人の調査とは
相続税の計算や、相続した不動産の名義変更をする際には、相続人を把握しておく必要があります。
相続人の人数によって相続税の基礎控除額が変わったり、相続登記の際に相続人全員の書類が必要になったりするためです。
相続人に該当する人
故人の財産を相続できる人は法律によって決められています。
遺言書がない限り、故人の配偶者と子どもが法定相続人です。
故人に子どもがいない場合は、故人の両親や祖父母が故人の配偶者とともに相続人になります。
両親などもいない場合には、故人の兄弟姉妹が相続人になります。
相続人の調査方法
相続人の調査は、故人の出生時から亡くなったときまでの戸籍謄本を途切れることなく調べる方法で行います。
これにより、故人に生き別れた子どもや認知した子ども、養子などがいないか確認できます。
戸籍は引っ越しや結婚などによって新しく作られることがあるため、故人の生活スタイルによっては調べる戸籍謄本の数が非常に多くなります。
相続人調査を弁護士に依頼するメリット
相続人の調査を弁護士へ依頼することで、手間をかけず、正確に調査できます。
手続きが進んだあとに新たな相続人が現れると、手続きを最初からやり直さなければいけなくなります。
見落としがないよう、調査は慎重に行わなければいけません。
もれなく正確に調査できる
弁護士に依頼することで、相続人の見落としを防げます。
調査に慣れていないと、戸籍に記載された養子縁組や認知の表記を見落としてしまうことがあります。
戸籍に記載される内容の一部は、戸籍を新しくした際に記載されなくなります。
一度見落としてしまうとその後も見落としたままになってしまうため、専門家へ依頼すると安心です。
とくにデジタル化される前の戸籍は、現在の戸籍と形式が違ったり、手書きで作成されたりと、読み解くことが簡単ではありません。
さらに市町村合併により、古い戸籍の所在地がなくなっている可能性もあります。
弁護士であればそのような戸籍も探し出し、正しく読み解くことが可能です。
手間のかかる手続きを代行してもらえる
弁護士が手続きを代行することで、相続人の方々は時間を有効活用できます。
身近な方が亡くなると、相続だけでなくさまざまな対応が必要になります。
第三者に任せられる手続きを第三者へ任せることで、相続人の負担を軽減できます。
故人や相続人の戸籍謄本は誰でも取得できるわけではありませんが、弁護士であれば職務に必要な範囲内で取得できます。
相続人をすべて調査したあとは、法定相続情報一覧図を作成しておくと、相続に関するさまざまな手続きに役立ちます。
法定相続情報一覧図の作成も弁護士へ依頼することが可能です。
相続人自ら作成することも可能ですが、相続人の数が多いと手間がかかります。
記載内容に不足があると相続の手続きに利用できないこともあるため、弁護士に依頼すると安心です。
トラブルに発展したとき、スムーズに対応を依頼できる
財産が多い場合や、不動産など分けることが難しい財産がある場合、相続の手続きを進める過程でトラブルが発生することもあります。
トラブルを個人間で解決することは難しく、弁護士に解決を依頼した方が良いケースも少なくありません。
相続手続きの初期段階から弁護士に依頼しておくことで、トラブルが発生した際にすぐに対応できます。
たとえば遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。
このとき不動産のような分割しにくい財産があると、協議が難航することもあります。
遺産の適正な分け方を判断することは難しく、分け方に納得できない相続人が現れると、協議はまとまりません。
協議をまとめるためには交渉が必要ですが、直接交渉すると、その後の親族関係に影響を与えてしまうこともあります。
このようなときに弁護士に対応を依頼することで、弁護士を代理人として法的な根拠をもとに交渉可能です。
トラブルが深刻化してからではなく、早めに依頼すると、こじれる前に対応できます。
まとめ
この記事では、相続人の調査を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。
相続人の調査は自分で行うことも可能ですが、手間がかかったり、見落としが発生したりすることもあります。
しかし弁護士に依頼することで、限られた時間の中で正確に調査することが可能です。
とくに故人に離婚歴があったり、引っ越しが多かったりする場合には、弁護士に依頼すると安心です。
弁護士には相続人の調査だけでなく、相続にまつわるさまざまなトラブルの相談も可能です。
相続の問題は弁護士までご相談ください。