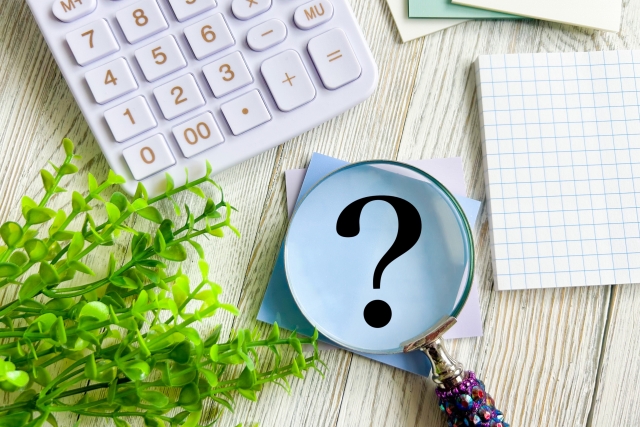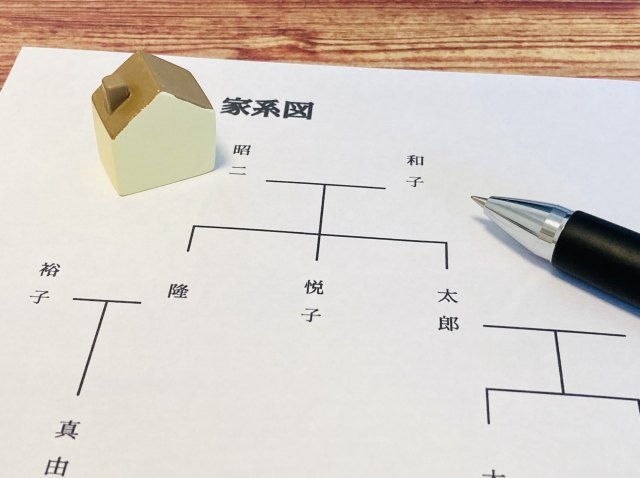被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分といって、最低限度の遺産の取り分が保障されています。
今回は、遺留分が侵害された場合の手続きの流れなどを解説します。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、贈与や遺贈により自己の遺留分を侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利です。
遺留分侵害額請求権には時効があり、遺留分権利者が相続の開始を知り、かつ、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しない場合、時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過した場合も、権利が消滅します。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求を行う場合、次のような流れで手続きを行います。
①遺言や生前贈与の確認を行う
遺留分を請求する場合、遺言書を確認し、ご自身の遺留分を誰がどの程度侵害していることを特定する必要があります。
また、遺言書だけでなく、被相続人が生前に行っていた贈与についても確認が必要です。
遺留分を算定する際には、原則として、相続開始前の1年間にされた贈与が対象となります。
ただし、相続人に対する贈与については、相続開始から遡って10年間にされたものであれば、遺留分侵害額を算定する際の基礎財産に含まれます。
したがって、まずは遺言書や、遡って10年間の生前贈与の記録を収集し、ご自身の遺留分が具体的にどれだけ侵害されているのかを正確に計算する必要があります。
この計算には、専門的な知識が必要となるため、弁護士に相談して進めることを検討してください。
②遺留分を侵害した者に請求の意思表示を行う
遺留分の侵害額が確定したら、その遺留分を侵害している者に対して、金銭の支払いを請求する意思表示を行います。
遺留分の権利を行使するためには、侵害された方の意思表示がなければ効力を生じません。
口頭での意思表示でも法的には有効ですが、後の水掛け論を避けるため、書面による意思表示を行った方が良いといえるでしょう。
遺留分の請求をしても相手方から返事がないような場合には、配達証明付きの内容証明郵便を送付してください。
これにより、いつ、どのような内容の意思表示を行ったかという証拠を残すことができます。
③遺留分を侵害した者と話し合いを行う
遺留分侵害額請求に相手方が応じた場合には、話し合いによって解決を目指すことになります。
算定した侵害額の根拠を示し、支払い方法や支払い期限などについて当事者間で合意を目指します。
話し合いがまとまり、遺留分を侵害した者から実際に金銭の支払いを受ければ、この段階で遺留分の請求は完了となります。
なお、話し合いにより合意した場合でも、遺留分の支払いが分割になったり、合意した日から払い込みの日まで期間が開く場合には、未払いを防ぐために強制執行のできる公正証書で合意書を作成するといいでしょう。
④遺留分侵害額調停を行う
話し合いによって合意が得られない場合や、相手が話し合いに応じようとしない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額調停を申し立てます。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、当事者双方の主張を聞きながら、合意による解決を目指して調整を行います。
調停はあくまで話し合いの場であるため、双方が納得できる和解案が見つかれば解決となりますが、相手方が頑なに請求を拒否したり、請求額について折り合いがつかなかったりした場合は、調停は不成立となり終了します。
⑤裁判で争う
遺留分侵害額請求調停が不成立に終わった場合は、最終手段として遺留分侵害額請求訴訟を地方裁判所に提起し、裁判で決着をつけることになります。
裁判では、双方の主張と提出された証拠に基づき、裁判官が遺留分侵害の有無や正確な侵害額を判断し、判決を下します。
判決は法的な拘束力を持つため、判決が確定すれば相手方はその判決に従って金銭を支払う義務を負います。
遺言自体の有効性を争うとき
遺留分侵害額請求の手続きを進める中で、遺言書の内容自体がおかしいと感じたり、被相続人の最終的な意思ではなかったのではないかという疑念が生じたりすることがあります。
たとえば、被相続人が認知症などで判断能力を欠いていたときに作成された遺言書であったり、形式的な要件を満たしていない遺言書であったりする場合です。
このようなときには、遺言無効訴訟を提起するという方法もあります。
遺言無効訴訟は、遺言書が法律上有効ではないことを裁判所に認めてもらうための手続きです。
遺言書が無効と認められれば、その遺言書に基づく遺贈はなかったことになり、遺産分割協議によって分割方法を決めることになります。
まとめ
今回は、遺留分侵害請求の手続きの流れや、遺言自体の有効性を争うときなどの解説をしました。
相続の問題は、家族関係を壊しかねないトラブルに発展することがあります。
火種が小さいうちであれば、不利益を最小限に抑えられる可能性があるため、お困りの方は弁護士にご相談ください。