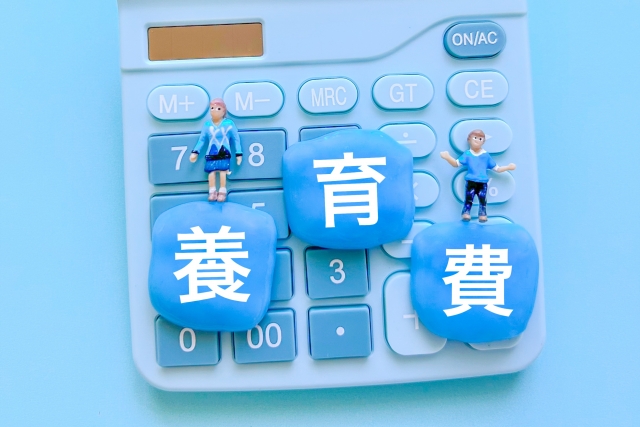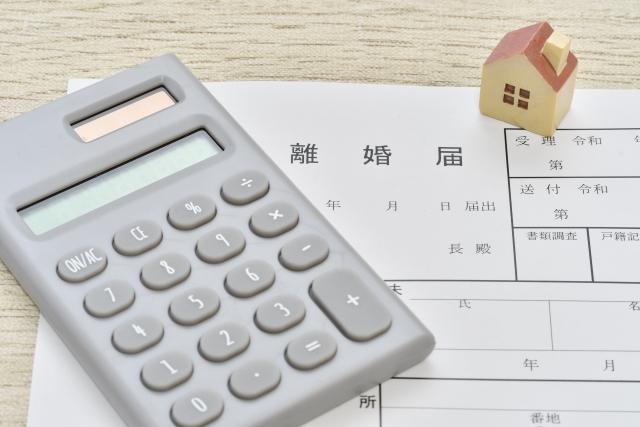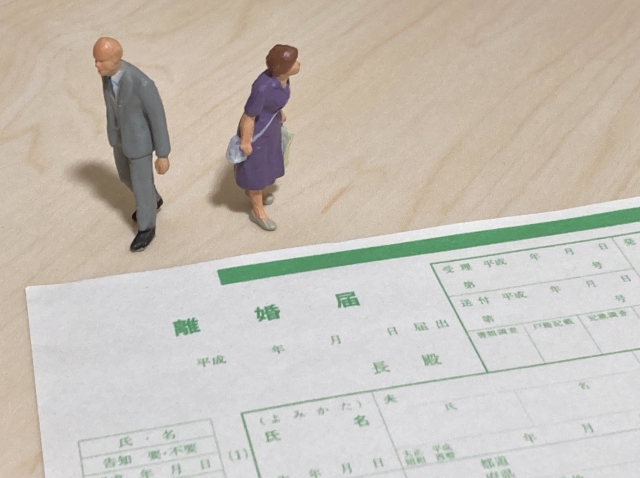日本では、離婚後に親権をどちらか一方の親が持つ単独親権が原則でした。
しかし、民法の改正により選択共同親権が今後導入されます。
この記事では、共同親権がどのような制度で単独親権とどう違うのか、また共同親権のメリットやデメリットについて解説いたします。
選択共同親権とは?
選択共同親権とは、2024年5月に成立した改正民法によって導入される新しい制度です。
父母が離婚した後も、父母の協議によって、親権を共同で持つか、または従来の単独親権とするかを選択できるようになります。
これにより、離婚後も父母双方が、子どもの養育や教育、医療などに関する重要な事柄について共同で決定する権限を持つことになります。
この制度の目的は、離婚後も父母が協力して子育てに関わる環境を整備し、子どもの利益を最大限に守ることにあります。
父母が合意できない場合は、家庭裁判所が子の利益を考慮して親権を定めることになります。
選択共同親権はいつ施行される?
選択共同親権を導入する改正民法は、2024年5月に成立しました。
この改正法は、公布の日から2年以内に施行されることが定められています。
したがって、具体的な施行日はまだ確定していませんが、遅くとも2026年5月24日までには施行される予定です。
単独親権との違い
単独親権とは、離婚後に父母のどちらか一方のみが親権を持ち、その親が単独で子どもの監護、教育、財産管理といったすべての親権を行使する制度です。
これに対し、選択共同親権は、親権を父母双方が共同で持つため、離婚後も父母2人が協力して重要な事柄を決定します。
単独親権では、親権を持たない親は、財産管理や監護などにおける法律行為の代理権・同意見を持ちません。
共同親権では、離婚後も父母の双方が子どもの成長に責任を持ち続けることになります。
選択共同親権のメリット
選択共同親権は、子どもの養育環境や父母の関係性に多くのメリットをもたらします。
離婚時の親権を巡る対立が緩和される
離婚時において、親権をどちらが持つかを巡る争いは、夫婦間の対立を激化させる大きな原因でした。
選択共同親権が導入されることで、親権を共同で持つという選択肢ができるため、親権をめぐる激しい争いが緩和されることが期待されます。
どちらか一方が親権を失うという認識が薄れることで、冷静な話し合いが進みやすくなります。
親子間の交流が増える
共同親権となることで、両親がともに子どもの養育に関する意思決定に関与できるようになります。
これにより、単独親権の場合に親権を持つことができなかった親が、子どもの生活や教育に積極的に関わる機会が増え、親子間の交流が増加することが期待されます。
子どもが両親から愛情とサポートを受けやすくなるという利点があります。
選択共同親権のデメリット
一方で選択共同親権はメリットばかりではありません。
ここからは選択共同親権のデメリットを見ていきましょう。
共同親権者がもめる可能性がある
共同親権では、子どもの進学や医療など、重要な事柄について父母双方が合意する必要があります。
しかし、離婚後も父母間の対立が残っている場合、意見が対立し、重要な意思決定が滞る可能性があります。
父母の協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐことになります。
離婚後も父母同士で関わる必要がある
共同親権を選択した場合、離婚後も子どもの養育に関する協議のために、父母同士で継続的に連絡を取り、意思疎通を図る必要があります。
これは、離婚によって相手と関わりたくないと考えている一方の親にとって、精神的な負担となる可能性があります。
協力関係が築けない場合、共同親権の運用が困難になります。
共同親権を選択できないケース
改正民法で共同親権が導入されても、特定の状況下では共同親権を選択できず、単独親権となる場合があります。
共同親権を選択できないケースとして、虐待やDVが挙げられます。
父母の一方から子に対する身体的虐待やネグレクトなど、子の心身に有害な影響を及ぼす言動のおそれが認められる場合、子の安全確保が不可能となるため、共同親権は選択できません。
また、父母の一方から他方の配偶者への暴行、脅迫、暴言といったDVのおそれが認められる場合も、単独親権となります。
DVの存在は、父母間で冷静な協議を行うことが困難であると判断されるためです。
これらの状況では、たとえ父母が共同親権を望んでも、裁判所は子の利益を害すると判断し、単独親権を命じることが義務付けられています。
まとめ
選択共同親権は、離婚後も父母の協議により共同で親権を持つことができる新しい制度です。
親権争いの緩和や親子交流の増加といったメリットがある一方で、父母間での対立継続や、離婚後も関わり続ける必要があるといったデメリットもあります。
離婚トラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。