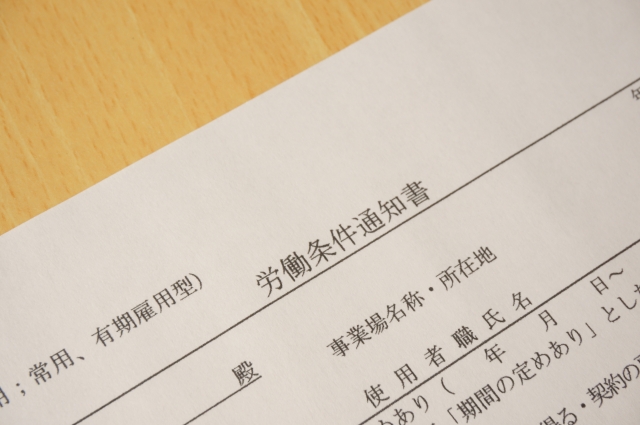企業間取引や個人間の貸し借りにおいて、売掛金や貸付金が期日通りに回収できないことは、事業の存続に関わる深刻な問題です。
債権回収は、内容証明郵便の送付といった交渉から始まりますが、債務者が支払いに応じなかったり、無視を続けたりすると、法的手段が必要になります。
この記事では、債権回収の方法と、弁護士に依頼すべきケースについて解説いたします。
債権回収の方法
債権回収とは、取引先や個人に売掛金や貸付金が期日までに支払われない場合に、その支払いを促し、最終的に代金を回収するための手続きです。
これは、事業の資金繰りを安定させ、経営リスクを回避するために不可欠です。
債権回収の方法は、大きく分けて交渉による回収と法的な手段による回収の2つがあります。
どちらを選択するかは、債務者の支払い意思や資産状況によって判断します。
交渉により回収する
債権回収の最初の、そして最も円満な手段は、債務者との交渉による回収です。
まず、電話やメールで催促することから始めます。
この段階では、相手の支払い遅延の理由を確認し、具体的な支払い予定日を取り決めることが重要です。
次に、内容証明郵便を用いることが有効です。
内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を、誰が誰に送付したかを郵便局が公的に証明するものであり、単なる催促以上の強い督促の意思表示となります。
時効の完成を一時的に中断させる効果もあります。
債権の時効は、権利を行使できると知ったときから5年、権利を行使できるときから10年です。
交渉を通じて、債務者と具体的な支払い計画について合意し、それを公正証書などの文書に残すことも重要です。
法的手段により回収する
交渉による回収が困難な場合や、債務者が支払いに応じない場合は、裁判所の手続きを利用した法的な手段に移行します。
まず、裁判所に支払い督促を申し立てる方法です。
これは、裁判所書記官が債務者に支払いを命じる手続きで、簡易かつ迅速な解決を目指せます。
次に、民事調停手続きを申し立てる方法です。
調停委員が間に入り、当事者間の話し合いで和解を目指します。
訴訟よりも柔軟な解決が期待できます。
最後に、訴訟を提起する方法です。
裁判官が双方の主張や証拠を吟味し、判決を下します。
勝訴判決を得た場合、強制執行として債務者の財産を差し押さえることができます。
債権回収を弁護士に依頼すべきケース
債権回収を弁護士に依頼すべきケースは以下の通りです。
債務者が支払いに応じない
債務者が内容証明郵便による催促にもかかわらず、支払いに応じない場合や、連絡が取れない場合は、弁護士に依頼すべきです。
弁護士は、依頼者の代理人として、債務者との交渉を粘り強く行い、法的な圧力をかけることができます。
また、債務者の資産状況を調査し、回収の見込みがあるかどうかを判断してくれます。
感情的な対立を避け、冷静な話し合いを進めるためにも、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
法的手続きによって債権回収する
支払督促、民事調停、訴訟提起、強制執行といった法的手続きによって債権回収を行う場合は、弁護士に依頼することが不可欠です。
これらの手続きは、法律や裁判所の運用に関する専門知識が必要であり、書類の作成や裁判所への出廷など、多くの時間と労力がかかります。
弁護士は、これらの手続きをすべて代行し、依頼者の負担を軽減します。
また、法的な主張を適切に行うことで、債権回収を成功させる可能性を高めます。
債権回収を弁護士に依頼するときの費用
債権回収を弁護士に依頼する際の費用は、主に着手金と成功報酬に分かれます。
着手金は、依頼時に支払う費用で、回収の成否にかかわらず発生します。
成功報酬は、実際に債権が回収できた場合に、回収額に応じて支払う費用です。
費用は、請求額の大小や、依頼内容の複雑さによって変動します。
弁護士によっては、回収の見込みが薄い場合は着手金を低く設定したり、完全成功報酬制を採用したりすることもあります。
相談無料を実施している弁護士事務所もあるため、まずは事情を相談し見積もりを出してもらいましょう。
まとめ
債権回収は、交渉から始まり、支払督促や訴訟といった法的手続きへと段階的に進みます。
債務者が支払いに応じない場合や、法的手続きを行う場合は、弁護士に依頼すべきケースと言えるでしょう。
債権回収でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。